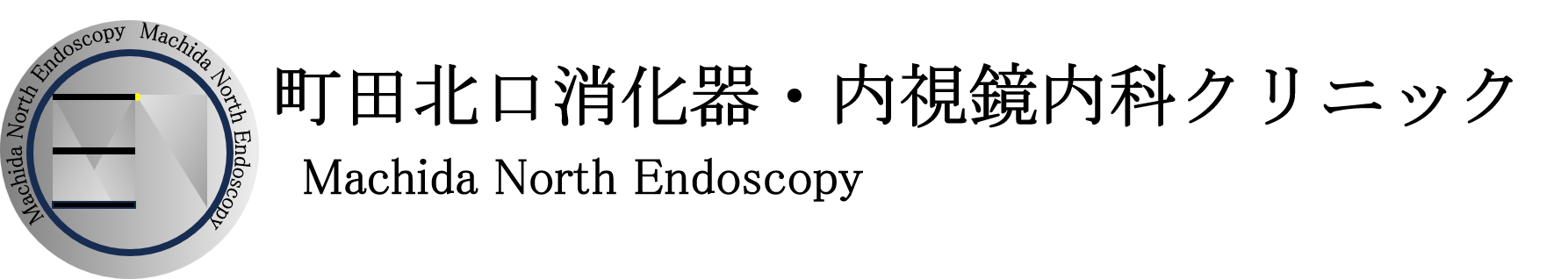ピロリ菌との関係
ピロリ菌とは
ピロリ菌(Helicobacter pylori)は、1983年に発見された、胃の粘膜に生息する細菌です。
ピロリ菌に感染すると、胃炎が慢性的に続き、さまざまな病気を引き起こす可能性があります。ピロリ菌との関連が深い主な病気は以下の通りです。
胃がん
胃潰瘍、十二指腸潰瘍
胃ポリープ
機能性ディスペプシア(機能性胃腸症)
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
ピロリ菌は、これらの病気を引き起こす原因の一つとして深く関連しています。特に胃がんの発生リスクを高めることがわかっており、ピロリ菌を除菌することで、胃がんの予防につながるとされています。
ピロリ菌の感染経路
ピロリ菌は、主に幼児期(6歳頃まで)に感染すると考えられています。
免疫機能が十分に発達していない乳幼児期に、ピロリ菌に感染した親や祖父母など、身近な大人から口を介して感染する「家族内感染」が主な感染経路とされています。また、集団生活を送る保育園や幼稚園などで、子ども同士が感染することもあります。
上下水道施設が整備された日本では、感染者のほとんどが、このような経口感染によってピロリ菌に感染していると考えられています。
なぜピロリ菌は胃酸に負けないの?
胃の中は、食べ物を消化するための強い酸(胃酸)で満たされており、通常、ほとんどの細菌は生きていられません。しかし、ピロリ菌には胃酸から身を守る特別な能力があります。
1.胃粘液の中にもぐりこむ
ピロリ菌はらせん状の形をしており、さらにべん毛という毛を動かすことで、胃の壁を覆う粘液の層の中にもぐりこみます。この粘液の中は、胃酸の影響が少ないため、ピロリ菌にとって安全な隠れ家となります。
2.胃酸を中和するアンモニアを作り出す
さらに、ピロリ菌はウレアーゼという特別な酵素を持っています。この酵素を使って、胃の中にある尿素を分解し、アンモニアを作り出します。アンモニアはアルカリ性なので、胃酸を中和する働きがあり、ピロリ菌の周りだけを中性にしてくれるのです。
このように、ピロリ菌は巧妙な方法で胃酸から身を守り、胃の中に住み着き続けています。
ピロリ菌と胃十二指腸潰瘍・胃がんの関係
ピロリ菌に感染したままの状態が長く続くと、胃の粘膜に炎症が広がり、徐々に慢性胃炎へと進行します。
慢性胃炎が続くと、胃の粘膜は弱まり、外部からのさまざまな攻撃(過度のストレス、塩分の多い食事など)を受けやすくなります。その結果、潰瘍ができやすい状態になったり、胃がんの発生リスクが高まったりすることがわかっています。
ピロリ菌は、これらの病気を引き起こす「土台」を作ってしまう、非常にやっかいな存在なのです。
ピロリ菌の検査方法
感染診断法は、内視鏡を用いる侵襲的な検査法と、内視鏡を用いない非侵襲的な検査法とにわかれます。
a内視鏡を用いる侵襲的な検査法
1.組織を採取して調べる方法
ピロリ菌は胃の中で不均一に分布しており、2箇所採取が望ましいとされています。
①迅速ウレアーゼ試験:胃の粘膜を少量採取して、その場でピロリ菌の有無を調べます。
②鏡検法
③ 培養法
2.胃液から調べる方法
核酸増幅法:ピロリ菌の有無だけでなく、除菌治療に用いられる抗生物質「クラリスロマイシン」に対する耐性遺伝子の有無も同時に調べることができます。
b.内視鏡による生検組織を必要としない検査法
①尿素呼気試験:診断薬を服用し、服用前後の息を採取して調べます。
②抗H. pylori抗体測定 :血液や尿からピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。
③便中H. pylori抗原測定:便を採取し、ピロリ菌の抗原の有無を調べます。
正確な検査のための注意点
正確な診断を行うために、一部の胃薬(プロトンポンプ阻害薬など)を服用中の方は、検査の2週間前から休薬していただくことが望ましいとされています。
また、ピロリ菌の除菌が成功したかを確認する除菌判定では、正確な結果を得るために、除菌治療終了後から十分な期間(当院では原則2カ月後、抗体法の場合は6カ月後)を空けて検査を行います。
ピロリ菌除菌療法
除菌療法には1週間抗生物質2種類と胃酸を抑えるくすり1種類を内服します
除菌判定には尿素呼気試験, 便中抗原法,抗体測定法が勧められます。
(1次除菌治療)
2種類の抗生物質と胃酸を抑えるお薬を朝と夕方の1回5個を1日2回、1週間しっかりと続けて飲んでください。除菌治療終了後、4-8週間以上経過後検査を行います。
(2次除菌治療)
1回目の除菌治療で除菌ができなかった場合は、薬を変え、再度除菌治療を行います。除菌治療終了後4-8週間以上経過後検査を行います。
(3次除菌治療)
保険診療上は2次除菌までです。保険外の治療となってしまいますが、患者様のご希望に応じて対応いたします。
ピロリ菌除菌療法除菌療法の副作用
ほとんどの方は特に症状なく終了します。
下痢、軟便で約 10~30%、味覚異常、舌炎、口内炎が 5~15%、皮疹 2~5%の報告があります。発疹、出血性腸炎などで中止となることもあります。
これらの副作用は事前に予想できません。
保険での除菌治療薬にはペニシリン系の薬が入っています。ペニシリンアレルギーの方は保険での除菌療法はできません。3次除菌と同様ですが、保険外の治療となってしまいます。患者様のご希望に応じて対応いたします。
ピロリ菌除菌療法の注意点
・確実にピロリ菌を除菌するためには、処方された薬は必ず服用するようにしてください。
・自己判断で服用を中止すると、除菌に失敗して、治療薬に耐性をもったピ口リ菌があらわれることがあります。
・すべての治療が終了した後、4-8週間以上経過してから(当院では原則8週以上あけるようにお願いしています。)行うピロリ菌の検査は必ず受けてください。また、検査に抗体測定を用いる場合はすべての治療が終了した後、6ヵ月以上あけてください。
・副作用があらわれたと思ったら、主治医または薬剤師に相談してください。
・二次除菌治療では、飲酒により腹痛や嘔吐, ほてり等が現れることがあるので,服用中は飲酒を避けてください。